ここまでお読み下さり有難うございます。
前編からの続きです。
2分でわかるガチな概要は前編で。
総合評価★★★★(4.0)
(理由は前編の概要にて記述。)
どんな強敵も粉砕するチームワークの姿がここに。
限られた資源で。
完全にスポーツのアプローチである所に得手不得手はあるかと思います。
アメリカ4大プロスポーツの史実から抽出・検証された組織心理学。
能力やデータだけを見る世相に一石を投じています。
並外れて先進的な無私無欲さこそが、卓越した組織を際立たせるものであり、時折成功するだけの組織には欠けているものなのである。(p94)
本書の前半は、その精神を重んじたチームワークで勝ち取った栄光の歴史とその考察から展開されました。
映画さながらの描写。
そこにあなたが勝つ為のチームワークのヒントを見つけてみては如何でしょうか。
前編ではそんな史実と、そこから得られる勝つ土台に焦点を当ててレビューしました。
もしあなたが本気で知りたいという場合、ここからお読みでしたら、
まずはより良い伝達の為に前編の概要を読む事をオススメします。
というか、いきなり後編を読んでもあなたのお役に立てないのです。
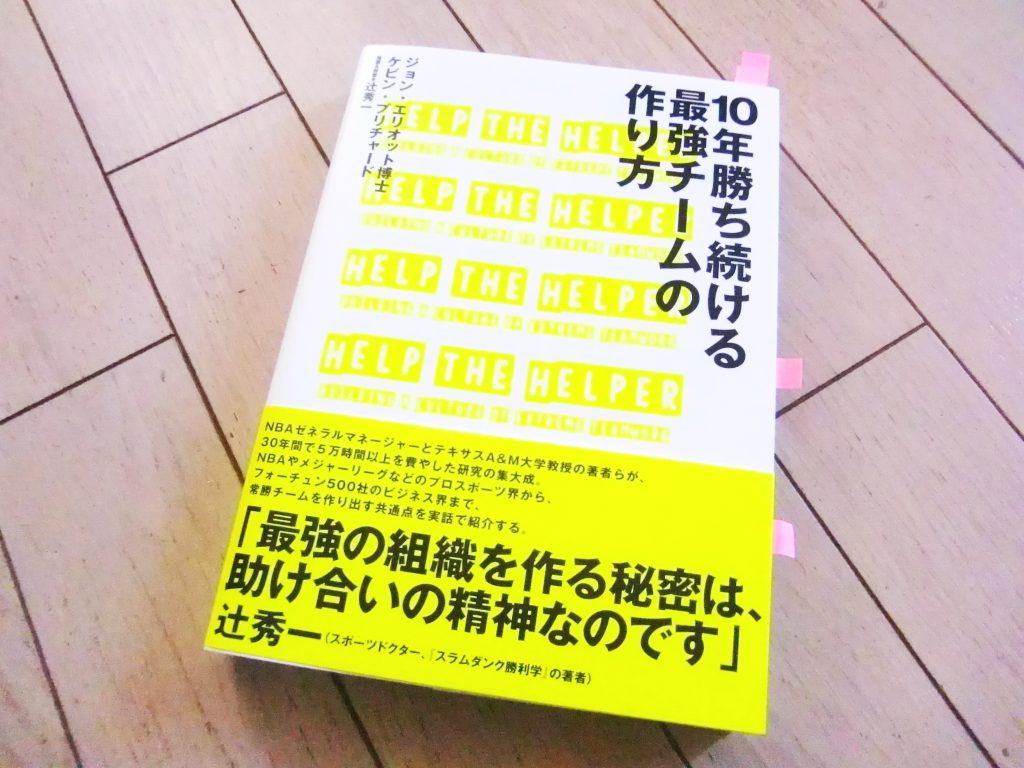
あなたが組織を持ち、指導する立場ならば活かせるお話。
スポーツが好きなら尚更です。
では、具体的にどんな所が活かせる?
「人」にクローズアップする事に徹した血の通った本のように感じています。
そこがポイントで、
これからお伝えする後半ではコミュニケーション術や指導法、更には精神医学やEQといった話に発展していくのです。
時折難解な箇所があり冗長気味にもなりますが、著者が提唱する”Help The Helper”の文化は一貫してブレがありません。
Contents
あなたが立場を手放すと、何かが起こる。
何だ?
指導法・コミュニケーション術の箇所は何回か読んでみたくなる印象です。
何故ならば、
一般的に考えられている事と比較し、逆転の発想の傾向があるからです。
それを噛み砕くのには少し時間と経験が要りそうです。
あなたは仕事を管理することを減らして、その代わりにチームメイトのエネルギーをもっとかきたてようとする意欲があるだろうか?(p226)
特にスポーツの世界の厳しい所は、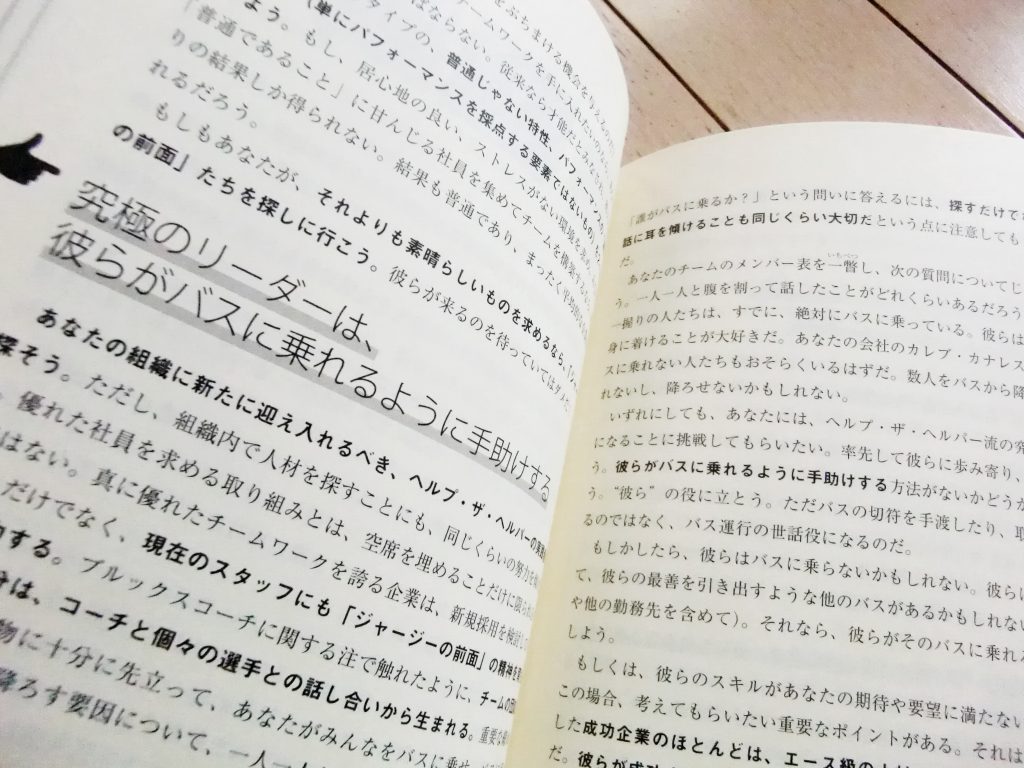
高額な年俸をもらっている才能溢れる一流のアスリートを育成・まとめる所。
想像してみて下さい。
もしあなたがそれをやらなければいけない状況になった時の事を。
私も仕事柄、内外問わず様々なプロの方達と相対する事が頻繁にあります。
血気盛んだったりもします。
慣れていて楽しんでいるのも事実です。
著者が言わんとしている事は概して、
やはりここでも、支える側に回る精神力。
やはりここでも、支える側に回る精神力。
管理を手放す事が意欲とモチベーションを高める事に一役買うと言います。
本書の真意を噛み砕くと、
ヒーローや権威にならない精神力と勇気。
一見、理解しがたく思えるかもしれません。
ですが、著者の目論見の1つである、史実から導き出されている成功法則は説得力を感じさせます。
彼がピラミッドの頂点にいるのは、ヘルプ・ザ・ヘルパーに価値を置いたからである。また、彼がピラミッドの頂点にいるのは、何か特別な存在の一部となることにより満たされる、人間として根本的な欲求があることを理解しているからである。(p113)
あなたの中で誰か名将と思える人物はいますか?
私は中盤以降を読み、確かに本書で語られているタイプの人物は多かったように思っています。
最後は情熱的に精神力の鍛錬。
同時に心を和らげていく優しく深みのある内容。
高尚な論理の展開に心を打たれていきます。
もし日常生活で何か張りつめているあなたがいたら、その何かが解けていく感覚に陥っていくかもしれません。
事実私はそうなりました。
何故だろうと今考えています。
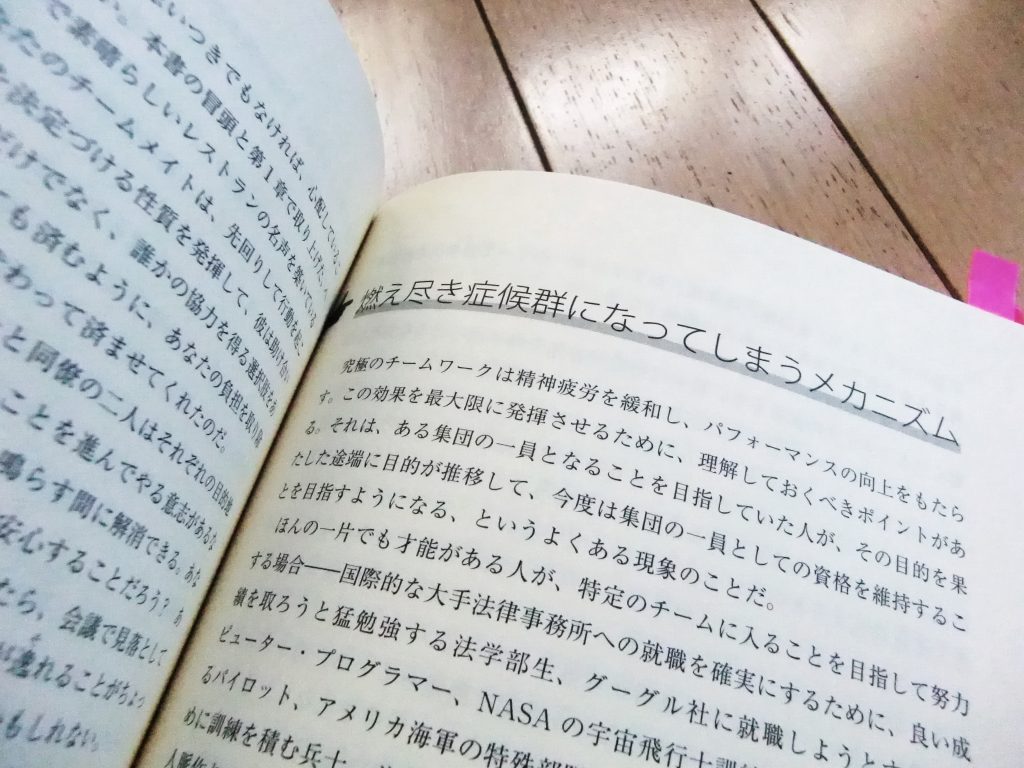
チームを率いて試練を乗り越えることは、神経の図太さを示すことではない。(中略)人間の持つ不屈の精神など高が知れている。人間とはそういうものだ。精神力は衰えたり、時々姿が見えないこともある。(p276)
今の自分を信じさせてくれる言葉の連続だったからかもしれません。
最後の締めで、そのような心持にさせてくれる書籍は久しぶりでした。
やや冗長な中盤もあったり、哲学的になっている感じもしましたが、視野の広さと深さを提供してくれたように思います。
人間の深さと弱さを再考させてくれるような、です。
この書籍が紹介されて気になった。
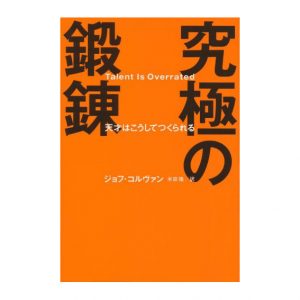
「究極の鍛錬」
2回ほどですが、著者がオススメとして紹介。
気になったので調べてみました。
興味をそそられたので、まずは読んでみようかと思います。
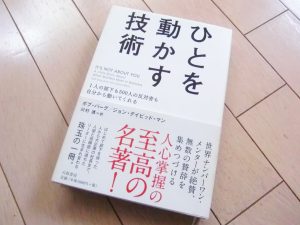
また本書を読んでみて、本書の基本概念はこちらの本にも通ずる深さを感じています。
「ひとを動かす技術」
ビジネスパーソンであれ、アスリートであれ、同じ人間。
人間の持つ基本原理・心理に違いは無く、両書が心の中で繋がっていくように思えたのでオススメしたいと思います。
そしてちょっと気になる事がありました。
下記の書籍はタイトルからもわかるかも知れませんが、人材データを使用する事で組織運営をするという内容です。
それだけを聞いてしまうと、本書と正反対のように思えてしまうかもしれません。
私も一瞬そう思いました。
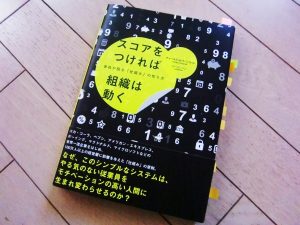
「スコアをつければ組織は動く」
ですが、その原理をよくよく考えてみると、
その根底には数字という万国共通・平等なものを使って、的確な評価の上で従業員のやる気を喚起させるものという思想があります。
数値でのランキングというものも基本的には否定。平等がテーマです。
タイトルで誤解されるという事についてもレビューで言及しています。
両書は同じ土俵に上げられません。
その理由は、
「スコアをつければ組織は動く」は、
現時点で評価されていない・認められていないビジネスパーソンに、平等な数字を使う事で評価に結び付けるという内容であり、
一方で本書は、
既に一定の評価を与えられている人達のさらにその先に焦点を当てているのかの違いだとも思うからです。
もし気になりましたら、上記の書も参考にしてみて下さい。
そして、ちょっと立ち読み。
そして、ちょっと立ち読み。
値段比較をしてみた。
- ダイレクト出版のHPから記事作成時点では直接購入不可能です。(会員宛の新刊図書の為)
会員になるにはこちらをご参照下さい。限定情報や書籍等の特典は付いてきます。 - アマゾン(Amazon)には新品・中古品ともにほぼ同じ価格で売られています。
アマゾンのサイト(検索済)へ - 楽天ブックスと楽天ブックオフでは購入不可です。
記事作成時点では見つかりませんでした。
※情報は変動する事がありますのでご了承下さい。
また、混乱を避けるため、恐れ入りますが具体的な数値は載せないようにしてあります。
ダイレクト出版の方では変動がほとんどないように思われます。
まとめ。
弱者の戦法。
全体を通して本書はそういう事を暗に言っているのだろうかと心の片隅で感じていきました。
限られた資源の中にあるのは、金銭でも設備でもなく人間。
その人間を活かし、エネルギーを最大にパフォーマンス化させる。
一枚岩になる為の拠り所、つまりチームワークが何よりも必要になる。
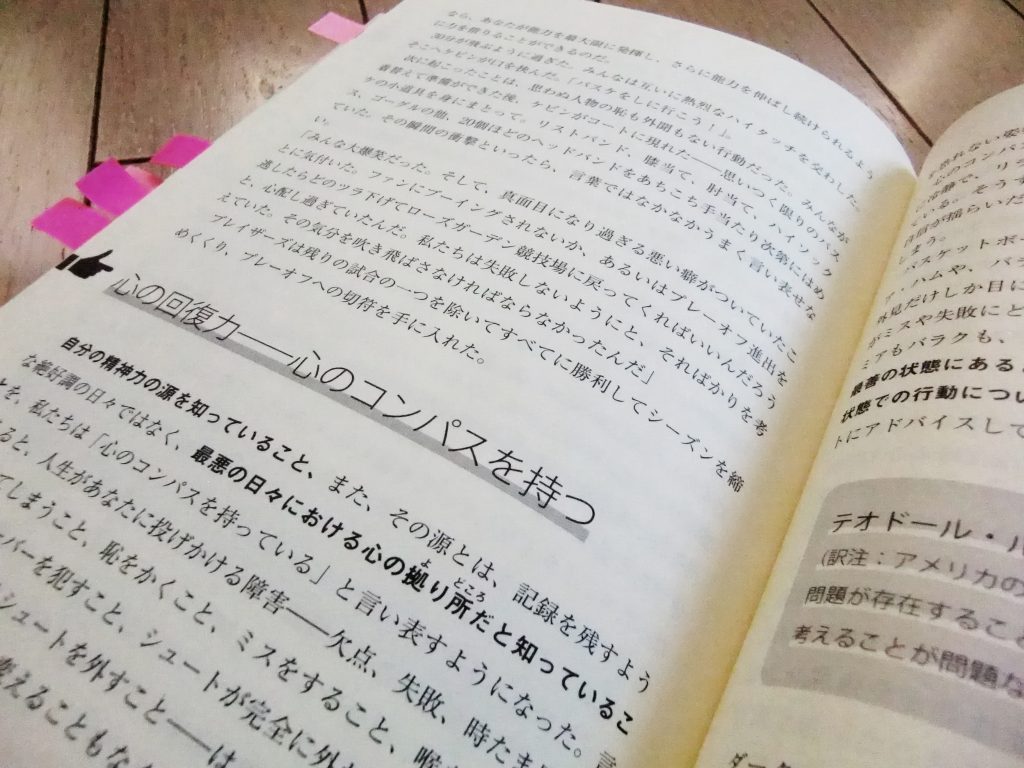
さざ波を大波濤に、つむじ風を竜巻にするには、その結束力が武器となり全てを打ち砕く。
その姿は弱小・貧乏球団が金満球団に打ち勝っていく秘密の戦法の数々を映画のワンシーンから見ているようでした。
金銭やヒーローに依存して思考停止になるのではなく、したたかに今あるものをより理解して活用する情熱を得たように思います。
心とか魂は、一見すると掴み所の無さそうでも続いていくもの。
金銭やヒーローと違って、無くならないもの。
それがタイトルの「10年」を表すのだと最後にわかりました。
ダイレクト出版
暮らしの中のフィールド・オブ・ドリームス最後に:
原動力となる愛を引き起こす方法を見つけない限りー祖国への愛であれ、神への愛であれ、理想の行動規範への愛であれ、隣で戦う人物への愛であれーあなたはリーダーとして失格だ。(p173)
愛だっ!
と言ってしまう事に恥ずかしさはありますか?
私は自身が指導する側に立った時、ためらいも無く使います。
その理由は?
教わる人達に、今、目前のものをもっと好きになってもらいたい想いからです。
それは決して綺麗事を言うのではありません。
何故、好きにさせるのか?
嫌いにさせるような指導法では全てが終わってしまう。
それと、好きにさせる事は誇りを持つ事に等しいのではないかと考えています。
その誇りこそがその人を豊かにもさせるし、強くもさせると信じています。
理不尽なまやかしの「厳しさ」や「ムチ」が強くするというのは、思考停止した幻想。
いろいろ試行錯誤する中で、その結論に辿り着きました。
指導するからには何よりも自分が進んで、本当の「厳しさ」や「ムチ」を深く考えなければいけません。
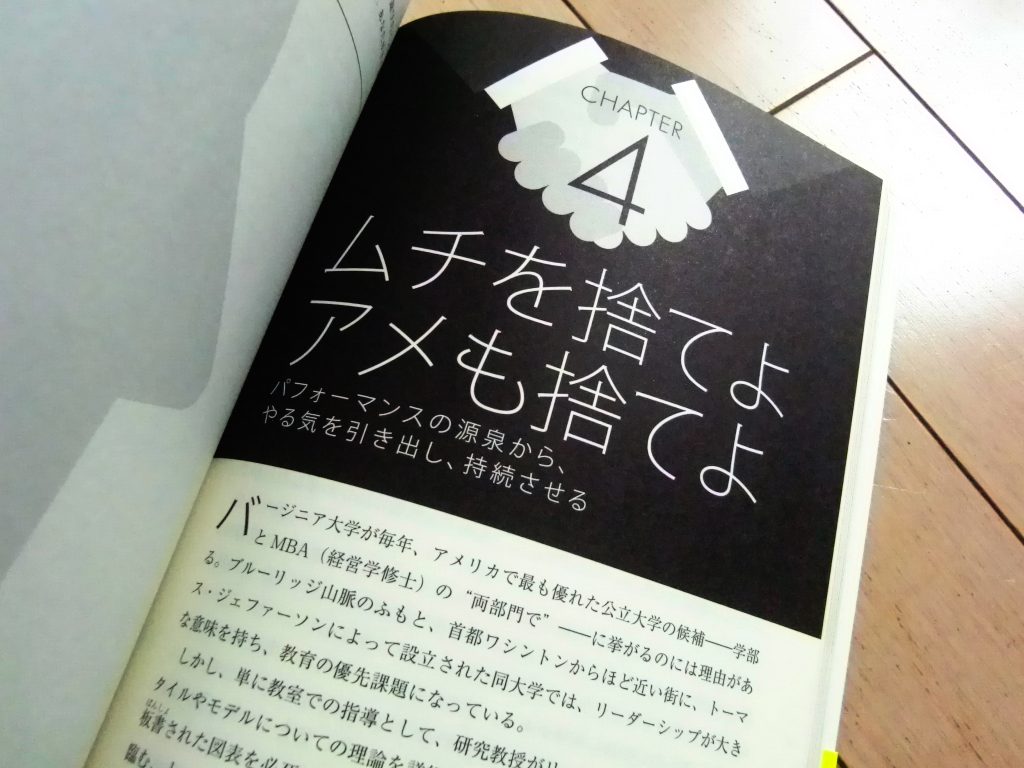
相手の愛を支えてみる事も、促してあげる事も、
組織を束ねる人間の使命や責任だと、
“Help The Helper”の文化の中で改めて悟らせてくれました。
指導者としても、組織を持つものとしても、意外な掘り出し物の良書だったように思っています。
暮らしの中のフィールド・オブ・ドリームス
「10年勝ち続ける最強チームの作り方」を見たい
<<前編で2分でわかるガチな概要を確認したい
| スポンサーリンク | スポンサーリンク |
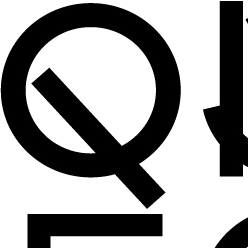
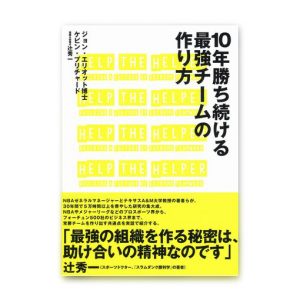
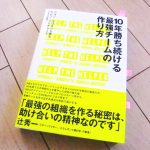


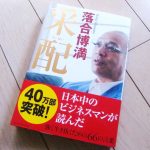
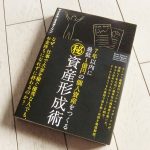

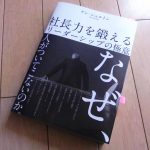

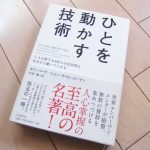

「ガチで独創的なレビュー:「10年勝ち続ける最強チームの作り方」(後編)」への1件のフィードバック
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)