真のレビューならこうしたい。
こういうのがあってほしい。
というお話です。
いきなり大それた表現になりました。
あなたにとってビジネス書に限らず、書籍を選ぶ際の悩みや理由はありますか?
その時々でいろいろあるかと思います。
多くのプロセスも踏むかと思います。
そこでまず、私の経験談をお話してもいいですか?
「こういうのがあったらいいのにな」
その疑問から生まれ、今に至ったお話です。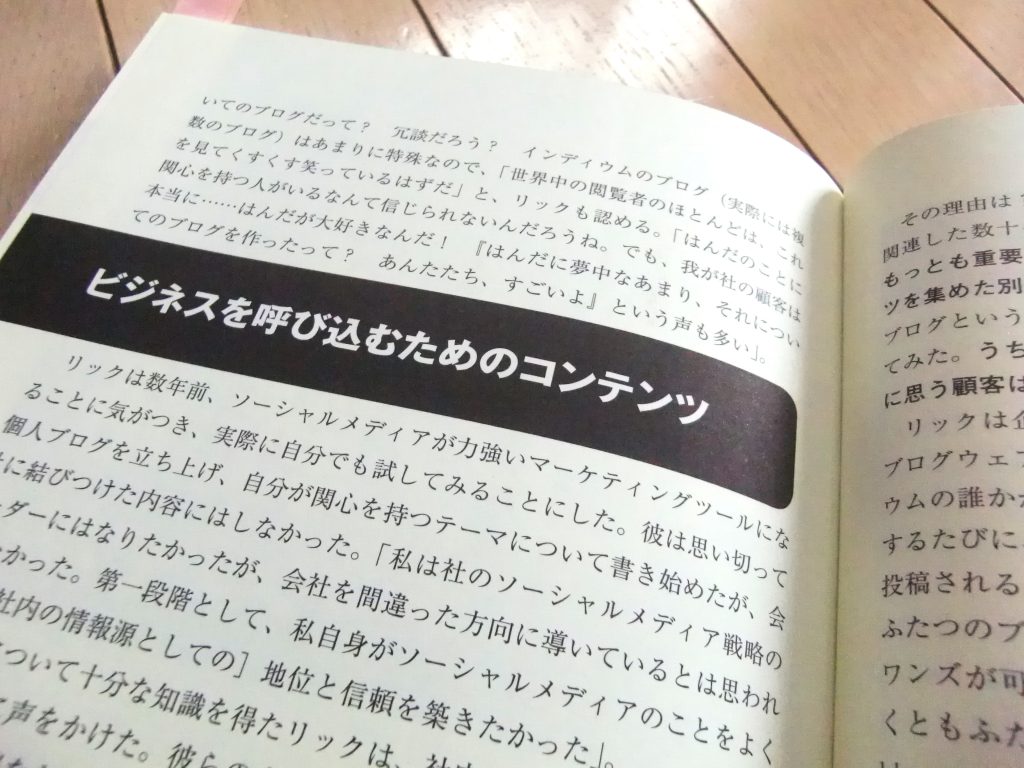
選ぶ理由は。
自身の中で起きた課題の克服の為に見聞を広めようとしたり、純粋な好奇心であったりと様々です。
そして目星をつけたものに必ずと言っていいほど必要になるのがリサーチです。
そのリサーチをじっくり時間を掛ける人、そうではない人といるかと思います。
現実問題として、お金を掛けて読むのならば、という気持ちがあるのも否めません。
私も例外ではないですね。
私はじっくりと時間を掛ける部類なのですが、
その吟味したいという行動の中での悩みが、私に多くの気付きをもたらせました。
そしてこのレビューに至ります。
Contents
リサーチの中で思った悩み。
アマゾンのレビューやブログ。
あなたもこのような所を参考にするかと思います。
私はと言うと、こちらの記事でも触れましたが、参考にするだけでなく、自分で書く側になった事もあります。
参考にする側の時に思い続けていた事。
内容をもうちょっとだけ知りたい。決め手が無い。
何を買えばいいのか。
いつもそんな想いがモヤモヤしながら残っていました。
どれを信じてよいのか?
レビューが多いほど有難いと思う半面、迷います。
こっちではああ言っていたけど、あっちではこう言っている、と。
そのレビューの言葉も、
その人のバックグラウンドによっても変わってくるので、単発的な感情だけで判断しても良いものなのか。
ターゲットや、客観的な意見が欲しいなと。
評論書や文芸書も多々読んで来た中で、学んできた事もあります。
批評する事の大変さ。納得してもらう事の大変さ。
自分は何を求めているのか?
いくら評価が良くても、自分の求めているものと合致しなければ、悪いという事にもなります。
逆に、そんな変な期待によって悪書扱いする世間も違うよねと。
どんな悩みを抱えて、何を求めている人に、どのような効果やメリットがあるのか。
それを伝える事の方が、勝手な感情や感想よりも信用出来るし有難い。
そう思うようになりました。
では、私はそうしてみようか。
自分の目で確かめよう。
買って成功したものも失敗したものも、自分の目で確かめてレビューに活かせる。
そうする事で先程のモヤモヤを気にしなくなりました。
そのモヤモヤですらも、このような形で役立てられるとの発想。
それは特別すごい事でもありませんし、素朴な発想なのです。
ここからは本音話の展開で、いささかストレートな物言いになりますが、
読者の方々に向けての真実ですので、ご容赦下さい。
真のレビューとは何だろう。
行うにあたり、それを追求したい。
これまでに書いてきたそんな沢山の想いがレビューに結びついた事をまずはお伝えしようと思います。
そして更には、それらの悩みや経験から導かれた、私が心掛けたいとする真のレビューでしたくない事、それは、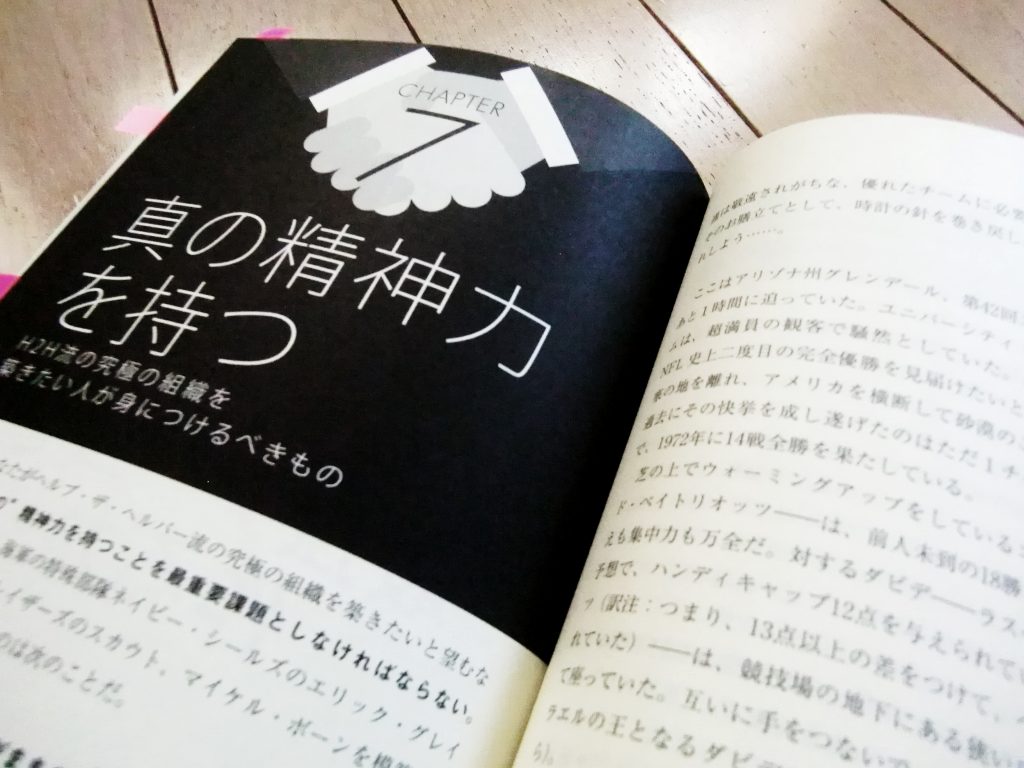
※参考文献:「10年勝ち続ける最強チームの作り方」
- ただ内容を書き連ねたり
(それは出版社のHPやアマゾンのレビューを見ればわかる)、 - それに対してどう思ったかや、どのように使ったかの考察も無く
(レビューの為のレビュー)、 - 実際にビジネスをしていない人や、永い時間の試行錯誤をしていない人が、言葉だけを書き連ねたり
(リアルさが無いのでわかります)、 - ただ感情をぶちまけただけになってしまう事
(感情なんて知った事ではない。自分に必要かどうかを知りたい)。
まず、誤解はしてほしくないのです。
仮にここ以外の場所でそういったものがあっても、私は決してそれを否定はしません。
貶めて自分の評価を上げるというようなセコくて姑息な手も使いません。
そんな相対的な事よりも、ポリシーの下で自分がやるべき事をやるだけだと思っています。
また仮に何らかの書籍を批判した所で対案を出さないのも卑怯だと思います。
誰も得はしません。
では、真のレビューでやるべき事としたい事は?
やるべき事は、このサイトに来て頂く意味も持たせていきたいと思う事です。
「何故ここなのか?」と。
それ自体も後々展開するマーケティングやブランディングにも通じていきます。
運営にあたり、それらの勉強にもなっている相互作用を感じています。
そしてこれまでの事を踏まえた上で、真のレビューとは、
良い事に対しても悪い事に対しても淡々としている事だと思うのです。
多角的にアプローチして、
相手にとって必要そうな事を見極めていく。
それが誠実さ。
それは基本理念でもお話しました。
リアルさを求める。
では次に、具体的に何を書くのか。
どのような情報を伝えたら相手は助かるかなとか、
この本の適している人はどんな人とか、
関連するものは何かあるのか(売れ筋・掘り出し物)、等々。
もっと言えば、自らの読むに至った経緯やリアルな臨場感。
自分が事業をしている中で得た経験や、進捗状況も踏まえてお話しするのも判りやすいかなと思います。
巷で、どんな良書と言われるものにも危険性はあります。
それは、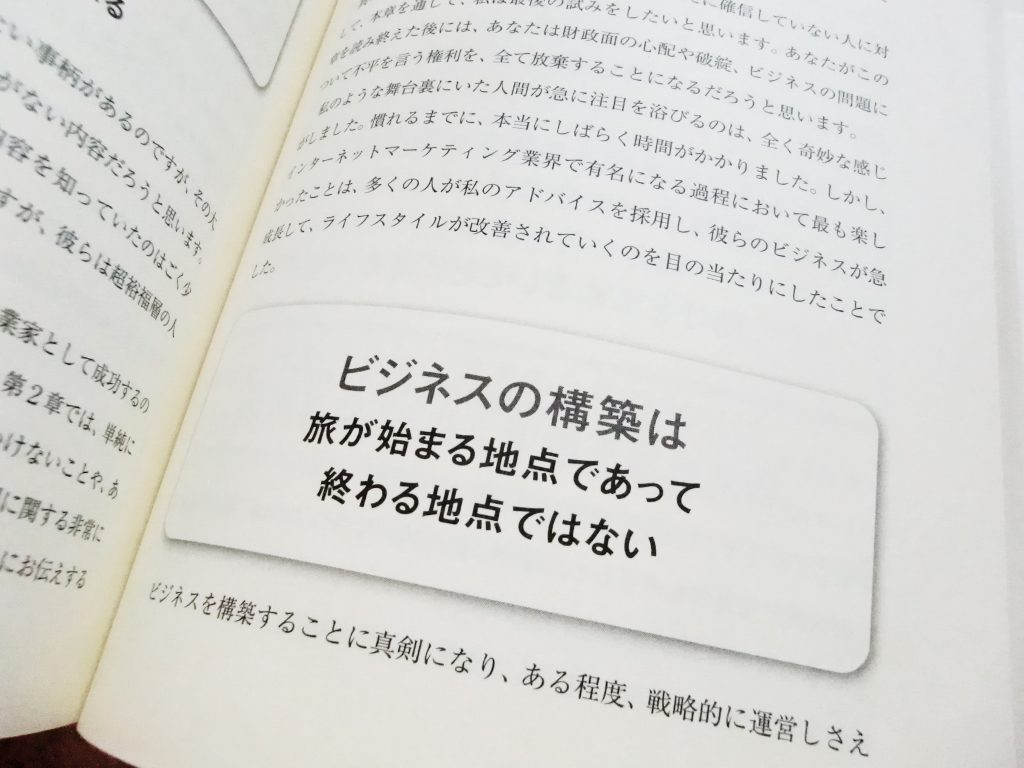
※参考文献:「インターネットビジネスマニフェスト 完全版」
ある段階に達する前に薦めても意味の無い物。
立場によって効果の有る物無い物。
予備知識が必要な物。
挙げればキリがありません。
またキリが無いのが書籍であり、レビューです。
いずれにしても、その不安を和らげられる所でありたいです。
実際の商売の現場で、本物の人間を相手にしているので良くわかります。
そして悩みながら勉強してきました。
これからもです。
その意味では、レビューの為のレビューがもしかしたら多い中で、リアルさのあるものを書く事が出来ると思っています。
何故そんな事考える?
その理由は本が好きだからです。
良い悪いは別にして、後々
「これ読んでおいて良かったな。」
と思ってもらえるのが理想です。
たとえそれが購入に至ろうとも至らなかろうともです。
本が好きで助けられてもきたから、そう思うのです。
責任もあるので、いい加減な事を言って薦める事もしません。
自らの悩みや経験がそんな事を悟らせました。
だから、そんなレビューを約束します。
| スポンサーリンク | スポンサーリンク |
あなたの知りたいを叶える、そして叶えたい関連記事。
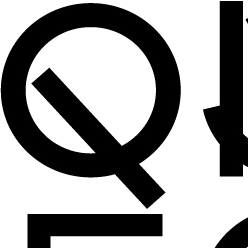




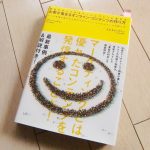

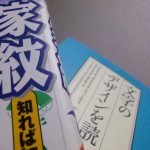
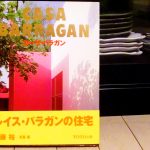

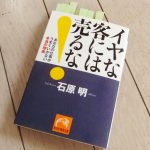
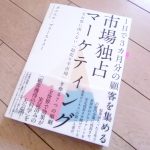
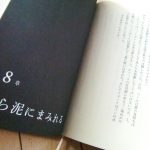
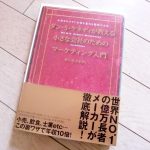
「ビジネス書を選ぶ時に感じた悩みが、真のレビューを悟らせた。」への2件のフィードバック
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)